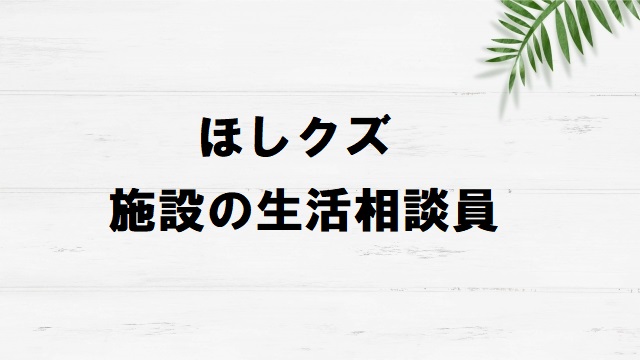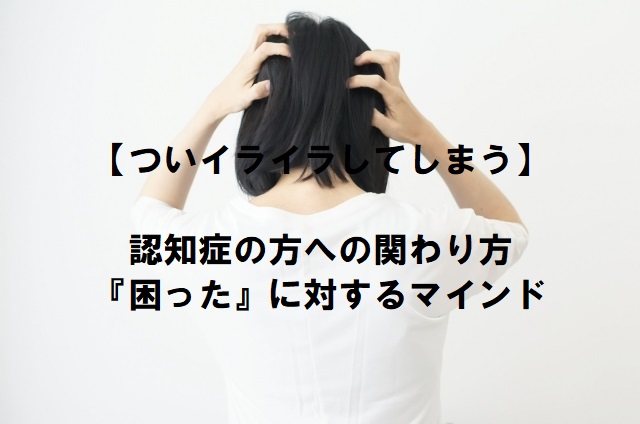こんにちは、『福祉のクズきち』です。
突然ですが、認知症のご利用者への関わり、きちんとできていますか?
他のご利用者の介助や記録、ケアプランの作成などやる事は無限にあるのに…
✅同じことを何回も繰り返し話してくる
✅急に立ち上がって歩き始める
✅急に怒り出したり、叩いたりしてくる
そんなことで、「今日も疲れた…」「大変だった…」という毎日に絶望的な疲れを感じていませんか?

特別養護老人ホームなら、多くの方が認知症の症状がある方たちだと思います。日々の介護の中で、疲れ切っていまっていては、質の高いサービスを提供する事が難しくなります。
そんな日々を少しでも変えたい思っている方は、この記事を読んでいただく事をオススメします。
認知症の方への理解
まず、認知症の方への関わりで「戸惑い」や「イライラを感じる」など、不安を抱えている人は、認知症についての知識を身に付ける事が大切です。
認証の方の行動の多くは、「行動・心理症状(BPSD)」と言われるもので、中核症状による不安や不快感から起こる症状になります。
「中核症状」「行動・心理症状」については、こちらの記事でお話しています。
「行動・心理症状(BPSD)」は、周囲の環境や職員の関わり方で改善が見込める症状と言われています。なので、まず職員がその事をきちんと理解しておくことが必要になります。
行動・心理症状(BPSD)が起こりやすい状況
認知症の方の気持ちを少し考えてみましょう。
どうでしょうか?
日頃の介護をしている中で、なんとなく思い当たりがある場面ではないかと思います。
このような状況の時の「あなた」に対する記録は「入浴を拒否された。」と書かれます。

でも、認知症の方にとっては、いつもこのような状況に置かれています。
こういう心理状態なんです。このことをしっかりと理解しておきましょう。
そうはいっても、働いている職員も人間なので、イライラしたり、うんざりしてしまうのは仕方がないと思います。私もそこは否定しませんし、私自身もそうなってしまう事もあります。
そんな時に少し立ち止まって考えたり、そういう感情になってしまった事をふり返って、次に生かしていく事が大切なんだと思います。
認知症の方への関わり方
そんな経験を積んできたからこそ、認知症の方へ関わる上でぜひ実践してほしいことがあります。
それは…
✅ご利用者の悪口を言わない
✅きちんと挨拶をする
✅落ち着いた関わりを心がける
という事です。

それが出来ないから困ってるんでしょ!
そうですよね。でも、行動が変わらなければ何も変わりません。意識してほしいんです。
いきなり
完璧にしなさいなんて言うつもりはありません。
ご利用者の悪口を言わない

ご利用者は、何かしらの事情を抱えて入所されています。ご本人たちも、必ずしも望んで入所したわけではなりません。
ご本人たちの苦しみや生活背景も知らずに悪口を言う事は、何のメリットも生み出しません。
逆に…
✅ご利用者に対するネガティブなイメージ
✅チームワークへの悪影響
を生み出すだけです。悪口は、あなたをネガティブな感情に引き込み、まわりのエネルギーを奪っていきます。
もしあなたのまわりで、悪口を言い始める人がいたら
- 「ちょっとトイレに…」と席を外す
- 話題を変える
- 他のご利用者の介助へ向かう
を試してみて下さい。
きちんと挨拶する
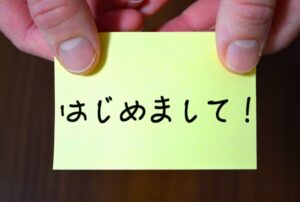
挨拶はコミュニケーションの基本です。会話のスタートは挨拶からです。
穏やかな口調で目を見て笑顔で挨拶しましょう。
認知症のご利用者にとっては、「毎日がはじめまして」です。いきなり知らない人に声をかけられるのと一緒です。
初対面の人に会ったら何をしますか?
挨拶ですよね。
毎日、毎回きちんと挨拶する事を心がけましょう。
落ち着いた関わりを心がける

人間は感情の生き物です。
相手がイライラした態度で話しかけてくれば、イライラします。
けんか腰で来れば、ケンカ口調になります。
人間は、相手の感情を読み取って、それに反応するんですね。
本当は丁寧に関わった方が良いのは分かっているはずです。
少し意識してみませんか?行動してみませんか?
最後に
ここまで、認知症の方に関わる上での考え方について解説しました。
介護職員の皆さまの日頃の業務は本当に大変だと思います。
『ご利用者の悪口を言わない、挨拶をきちんとする、落ち着いた関わりを心がける』
この3つをメモして、フロアのケアセンターやパソコンの横などに貼り付けて下さい。
必要なのはすぐに行動をすること、アウトプットすることです。
普段から職員が共通の認識を持って、意識できる環境を作っていきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
認知症ケアは高齢者ケアの原点です。
これからますます必要になる高齢者介護の未来を一緒に作っていきましょう。